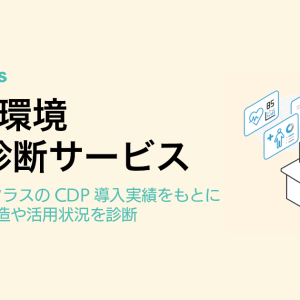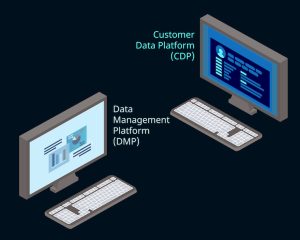高度なデジタルマーケティングを求める上で注目されているツールの一つが、CDPです。顧客一人ひとりのデータを収集・一括管理し、分析・活用するためのプラットフォームで、その需要は拡大傾向にあります。しかし一方で、「うまく活用できない」「十分な効果が得られない」といった企業も見られるようです。そこで本記事では、導入したCDPが停滞してしまう原因とその対策をよくある失敗例を交えながら紹介します。
CDPとは?
CDPはCustomer Data Platform(カスタマー・データ・プラットフォーム)の略語で「顧客のデータ基盤」とも呼ばれています。
基本機能はデータの収集と統合、分析です。社内で分散しがちな自社保有の既存顧客データを主体に、連携させた外部サービスツールから得たサードパーティーデータも統合して一括管理し、分析・活用できます。
例えば、個人の詳細情報と行動履歴や購買歴といったデータをCDPと紐づけることで、顧客データを統合的に管理でき、そのデータをもとに顧客のニーズを分析できます。
分析結果を活用することで、より効果の高いマーケティング施策につなげられます。
詳しくは「CDPとは_意味や基本性能_導入メリット_課題などを徹底解説」をご覧ください。
CDPをうまく活用できないパターンとは
このように高度なデジタルマーケティングにおいて大きな役割を果たすCDPですが、なかには活用がうまくいっていないパターンもあります。大きく2つに分けて解説します。
導入後にほとんど利用できていない
CDPの導入には準備や各部署との連携など「すべきこと」が多く、相応の手間と時間がかかってしまいます。しかし、手間と時間をかけて膨大なデータを統合したものの、CDP構築で息切れしてしまい、施策に生かされていないケースが少なくありません。また、CDPの活用範囲を大掛かりにしてしまうとすぐに効果が見えづらく、導入したものの早期に運用を諦めてしまう場合もあります。
仕様書と異なるイレギュラーな形式のデータが取り込めない
取り込みや集計の段階で発覚しがちなパターンです。
データの中にエラー数値が入っていたり、テキストの形式が異なっていたりして取り込めない、もしくは紐づかない場合があります。そうすると設計のやり直しを余儀なくされ、変換プログラムの構築といった手順が増えてしまい、結局CDPを活用できない要因となってしまいます。
CDP活用がうまく進まない原因とは
先ほど紹介したパターンを踏まえ、CDP活用がうまく進まない理由を具体的に解説していきましょう。
使用目的が明確化していない
「自社保有のデータの活用にまずはCDPを導入しよう」「使うかもしれないのでまずはデータを集めておこう」といったあいまいな理由での導入では、CDPの活用は難しいでしょう。データを取り込むこと、システムを構築すること自体が目的となってしまい、データ分析や実行まで至らないことがあり、活用を停滞させる大きな要因となります。
目的に合った予算組みができていない
CDP導入から運用までには、もちろん相応の費用がかかります。活用範囲や期間によっては膨大な投資額となるでしょう。そのため、目的に合ったCDPを選んでいないうえに、導入時から規模を大掛かりにしてしまうと費用対効果が見えにくくなります。結果、管理部門と現場の目的意識が乖離し、計画が頓挫してしまいます。
保有のデータ量が不足している
まず初期データ量が不十分であることが活用できない一因でしょう。CDPは収集したデータから統合、分析、実行していくものです。データ量が不十分であるとこれらの行程が滞ってしまいかねません。
その一方で、一元管理した大量のデータの中身を把握できていないという点も活用を妨げる一因となります。目的意識なくデータを集めることだけに注力してしまうと、どこにどのようなデータがあるのか分からなくなってしまい、分析・実行に至らなくなる場合もあります。
人材が不足している
CDPの導入・活用を他の仕事と兼任で行うのは難しいものがあります。導入はもちろんですが、その後運用でもデータ統合や分析など多くの工程があるためです。継続して運用していくためにも専任の担当者を置くのが賢明でしょう。しかし、そもそも社内にCDPに詳しい人がいない、専任で置く人材がいないという企業もあり、導入したものの活用できずにいる要因となっています。
ブラックボックス化している
「CDP運用をの担当者が交代したが、中身が複雑化しており引き継ぎが難しい」という問題あります。退職や異動、転勤といったことで専任が定まらず、運用方法の引継ぎがうまくなされなかったことでCDPがブラックボックス化してしまうケースもあります。
各部署の連携が取れていない
CDPで企業が保有するデータを一括で管理する際、部署を横断したデータを管理するケースも多くなりますが、それぞれの部署でバラバラに管理していたデータは使用目的などが異なる場合もあるため、部署間の連携がうまく取れていないと運用がスムーズに行かないケースもあります。最悪の場合、運用が止まる恐れもあるでしょう。
また、セキュリティー部門と連携していないと、CDPの中に個人情報を入れる可否を確認しておらず、集めたデータを使えないといった事態に陥る場合もあります。
CDP活用の課題解決方法
では、これらのCDPをうまく活用できていない課題に対し、どのようなことをすれば良いでしょうか。解決策を解説していきます。
導入前に目的を明確にする
どのような目的のため、どのようなデータを集めるのか、事前にCDPの導入目的を明確にして計画を立てておく必要があります。
たとえば、「最適な広告」を目的とした場合は広告自体の設定だけに留まらず、顧客へのサービス提供やビジネスの再設計の可能性を含めて目的を定めましょう。それぞれの場合にどのようなデータが必要か、といったように具体的に細かく計画しておきます。
このようにCDPをうまく運用するには「事前の準備」が重要なポイントです。
先を見据えた予算組みをする
CDP導入前から施策に必要なCDPツールを含めたコストだけではなく、継続運用のため2、3年先を見据えた予算組みをしておくと、各部署ならびに費用対効果を求める管理部門の理解を得やすいかもしれません。そのためにもシステム構築はもちろんですが、分析・実行の結果から議論や検討を重ねて再構築できるように、予算や期間に余裕を持たせておくと良いでしょう。
CDPで管理するデータを事前にチェックしておく
データ処理に入る前に、実データとなるビッグデータを入念にチェックしておく必要があります。たとえば、顧客の紐づけをIDなどの数字で行う場合、そこに顧客の氏名などのテキストが入っていないかの確認をしましょう。また、変換プログラムが必要なデータがあるかどうかなどを事前に把握しておくと、CDP構築がよりスムーズになります。
運用ルールを定めておく
あらかじめ運用ルールを定め、各種の仕様書を作成しておくことが大切です。たとえば、新たなデータを追加する際、担当者が変わっていたため、どのプログラムを修正すれば良いか分からず、運用が滞ってしまうことも考えられます。適切な仕様書があれば、属人化・ブラックボックス化を防げるとともに引き継ぎが容易に行えるでしょう。
組織の連携や部署間の調整
CDPは多岐に渡るデータを一元管理できるという大きなメリットがありますが、各部署が扱うデータをどこにどう統合するのか、誰が管理するのか、といった問題が出てきがちです。その調整には時間をかけ、各部署の理解や連携を得ておきましょう。CDP構築の際にはさまざまな部署の人材をプロジェクトに入れておくと調整がスムーズです。その上でデータ管理の窓口を一本化しておくと、運用し易くなるでしょう。
CDP活用に長けた人材の教育・採用を行う
もともとCDPに詳しい人材を採用するのも一案ですが、IT業界の人材不足の折、社内でIT人材の教育やリスキリングなどを積極的に行うことが大切でしょう。CDPに長けた人材が多く育てば、専任担当者の選択の幅が広がります。
外部の専門家に相談する
準備や人材育成に注力してもやはり社内だけではCDPの活用が進まないケースもあるかもしれません。その際は外部の専門家に相談することも検討する必要があります。効率的に結果を出し、さらなる施策の構築がスムーズにできるでしょう。
CDPをよりスムーズに活用するには外部の専門家に相談を
より効果の高いマーケティング施策を実行するためには顧客データの収集、保管、分析が必要であり、そのための基盤導入や構築は大きなポイントとなります。なかでも、顧客データを一括管理できるCDPは重要です。
Legolissは、データを軸とした企業のマーケティング全般をサポートするデータ活用コンサルティングを実施しています。企業のCDP環境を分析し、その効率性と効果性を高めるための診断サービス「CDP環境 健康診断サービス」も提供しており、現状の自社のCDP環境を把握するには有効でしょう。外部の専門家への相談を検討している場合は、ぜひお問い合わせください。